安藤ハザマ(社長:野村俊明)は、メック エックス社(本社:米国テキサス州ヒューストン、社長:ダグラス D.カーヴェル。以下、MECX社)および同社の日本総代理店であるパシフィック リム サービス社(本社:米国アラスカ州トラッパークリーク、社長:茅野 徹。以下、PRS社)との間で、PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染土壌浄化のための「PCB酸化分解処理技術」に関する技術提携契約を締結しました。
MECX社が開発したこの技術は、米国環境保護庁(EPA)で認められており、既に米国ミシガン州において、PCBやダイオキシンなどの難分解性物質汚染土壌の現位置浄化で数多くの実績があります。
PCB汚染土壌の処理には、加熱方式(一定の温度以上に加熱してPCBを気化分離)、溶融方式(高温で汚染土壌を溶融する過程でPCBを分解)、洗浄方式(洗浄水中にPCBを抽出して土壌と分離)などがありますが、これらの方式は、多大な熱源や大型の装置を必要とするなど、処理コストが高くなりがちでした。
一方、PCB汚染土壌であっても、汚染の状況が法令に定められた第二溶出量基準(※1)(0.003mg/L)以下であれば、管理型処分場へ埋め立て処分することが認められています。当社はこの点に着目し、第二溶出量基準の数倍程度の汚染土壌を低コストで浄化する技術として同技術の採用を検討してまいりました。そして、日本国内での施工方法と、それに合わせた事前適用性試験の手順が確立できたため、同技術の採用を正式決定し、提携契約に至りました。
「PCB酸化分解処理技術」は、PCB汚染土壌を掘削した後、現位置で酸化剤(過硫酸ナトリウム)(※2)と活性化剤を添加してPCBを酸化分解する工法(図1参照)で、第二溶出量基準を超過し、かつ含有量が100mg/kg程度までの汚染土壌の浄化に適しています。特殊な活性化剤を用いることで酸化剤の酸化能力が2か月程度継続するため、低コストで確実にPCB汚染土壌を浄化できます。
当社が実施した事前適用性試験では、酸化剤をPCB汚染土壌重量の2%の割合で添加した場合に、添加後2週間で第二溶出量基準以下まで浄化できることが確認できました(表1参照)。
当社は今後、国内において本技術を各方面に提案し、PCB汚染土壌の浄化事業を進めてまいります。また、PCB汚染土壌の浄化・削減を通じて、土壌環境の修復・保全に寄与してまいります。
なお、本技術については、2014年10月15日(水)から17日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展」への出展を予定しています。
-
第二溶出量基準
土壌汚染対策法(2003年2月施行)に基づく汚染土壌の基準の一つ。特定有害物質の種類ごとに土壌溶出量基準の10~30倍の溶出量に相当する値が決められている。 -
酸化剤(過硫酸ナトリウム)
製品名「Krozur®(クロージャー)」。ペルオキシ ケム社(本社:米国ペンシルベニア州フィラデルフィア、社長:ブルース ラーナー)が日本国内での土壌浄化剤としての専用実施権を持ち、当社は、日本総代理店のPRS社を通じて、PCB汚染土壌処理用薬剤として利用する契約を締結している。
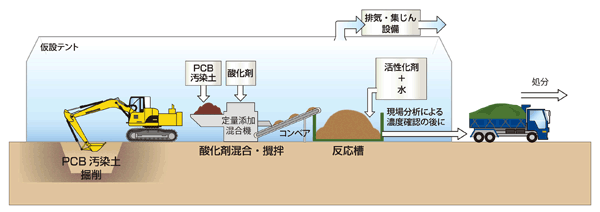
図1:酸化剤によるPCB汚染土壌浄化(イメージ)
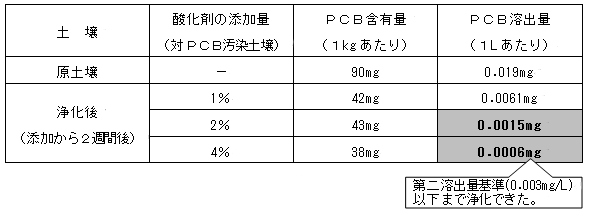
表1:酸化剤添加によるPCB汚染土壌の浄化効果