HISTORY
-
1928
-
1960
-
1963
-
1997
-
2000
-
2004
-
2013
-
1928年
「愛媛県庁」竣工
愛媛県
現在も都道府県庁舎として使われている近代洋風建築物。特徴的なドーム状の屋根を中心に左右対称のつくりで、空から見ると鳥が翼を広げたようになっている。
-
1960年
「中山競馬場観覧スタンド」竣工
千葉県
日本4大競馬場の一つで、地上3階・地下1階の観覧スタンドを手がけた。当社はその後も増築・改築工事を担当し、1990年には地上6階・地下1階の新スタンド工事も建設した。
-
1963年
「黒部ダム」竣工
富山県
高度経済成長期の電力不足を補うため、発電を目的として建設されたアーチ式コンクリートダム。世紀の大事業といわれた黒部ダムは、さまざまな困難を克服し、着工から7年後に完成した。高さは186mで現在も日本一。
-
1997年
「ペトロナスツインタワー」竣工
マレーシア
高さ451m・88階建て、完成した当時世界一の高さを誇った超高層ビルである。このツインタワーのうちタワー1の建設を担当した。
-
2000年
「トッパン小石川ビル」竣工
東京都
曲面のガラスカーテンウォールが印象的な地上21階・地下3階の建物で、高層オフィススペースと印刷博物館やクラシック中心の音楽ホール、レストランなどを併設した複合施設である。
-
2004年
「大洲城天守閣復元工事」竣工
愛媛県
戦後初めて木造の4層4階の天守を完全に復元。19mという復元された木造天守としては日本一の高さを誇る。
-
2013年
安藤建設株式会社と株式会社間組が合併し、株式会社安藤・間が発足。





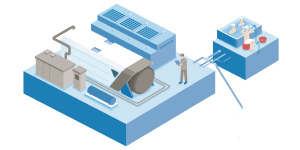
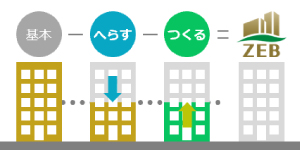











 16
16










